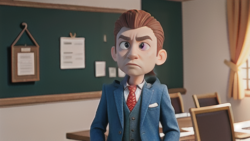経済の用語
経済の用語 沖縄振興を支えたODFC:その役割と歴史
沖縄は、美しい自然と独特の文化を持つ地域として知られていますが、本土復帰後も経済的自立という課題を抱えてきました。その課題解決の要として、1972年に設立されたのが沖縄振興開発金融公庫、通称ODFCです。
ODFCは、沖縄県に根ざした金融機関として、県内の企業や個人事業主に対して、事業資金の融資や経営に関する相談など、幅広い支援を行っています。単に資金を提供するだけでなく、事業計画の策定から実行、その後の経営改善まで、伴走型の支援体制を整えている点が特徴です。
具体的には、観光や情報通信、農林水産業など、沖縄の強みを生かした産業の育成に力を入れています。また、雇用創出や新事業の創出を支援することで、地域経済の活性化にも貢献しています。
ODFCは、沖縄経済の成長を支える原動力として、これからも重要な役割を担っていくことが期待されています。