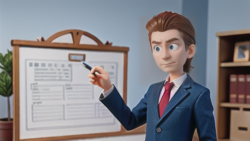経済の用語
経済の用語 経済の健康診断!GDPってなに?
- 国内総生産(GDP)とは国内総生産(GDP)は、ある国の経済規模を測る上で最も重要な指標の一つです。 GDPは、Gross Domestic Productの略称であり、日本語では「国内総生産」と訳されます。簡単に言うと、GDPは一定期間(通常は1年間)に、国内で生産された全ての最終的な財やサービスの市場価値を合計したものです。 つまり、ある国で1年間にどれだけの価値を生み出したのかを示す指標と言えるでしょう。例えば、自動車や家電製品といったモノだけでなく、美容院での散髪や病院での診察といったサービスもGDPに含まれます。これらの財やサービスの生産活動が活発であれば、GDPは増加し、経済が成長していることを示します。逆に、生産活動が低迷すれば、GDPは減少し、経済は縮小していることになります。GDPは、経済の現状を把握するだけでなく、政府の経済政策の立案や、企業の経営判断、投資家の投資判断など、様々な場面で活用されています。