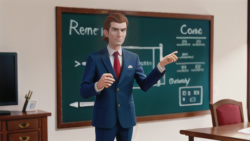経済の用語
経済の用語 EU: あなたの生活への影響とは?
EUとは、ヨーロッパ連合(European Union)の略称で、ヨーロッパの多くの国々が加盟する国際組織です。その目的は、加盟国間で協力し、戦争のない平和な状態を維持しながら、人々の暮らしをより豊かにすることにあります。現在、EUには27の国々が加盟しており、経済、政治、社会、文化など、様々な分野で協力体制を構築しています。
EUの特徴は、単なる貿易協定の枠組みを超えている点にあります。加盟国間では、人、物、サービス、資本が自由に行き来できるようになっており、まるで一つの国のような一体感を持ち合わせています。また、共通の通貨であるユーロを導入している国も多く、経済的な結びつきも非常に強いと言えます。
EUは、加盟国にとって、より広大な市場と、より多くの機会を提供する存在です。企業は、多くの国で商品やサービスを提供できるようになり、消費者も、より多くの選択肢から商品やサービスを選べるようになります。また、EUは、環境問題やエネルギー問題など、地球規模の課題解決にも積極的に取り組んでおり、国際社会においても重要な役割を担っています。