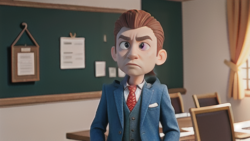 経済の用語
経済の用語 国内総所得(GDI)とは?分かりやすく解説
- 国内総所得(GDI)の概要国内総所得(GDI)は、一定期間(通常は1年間)に、国内で新たに生み出された財やサービスの付加価値の合計を表す経済指標です。これは、言い換えれば、国内で経済活動を通じてどれだけの所得が生まれたかを示す指標とも言えます。私たちが日ごろニュースなどで耳にする「経済成長」や「景気」といった言葉は、このGDIと密接に関係しています。GDIが増加すれば、国内でより多くの財やサービスが生産され、人々の所得も増加していることを意味するため、経済は成長し、景気は良くなっていると判断できます。逆に、GDIが減少すれば、経済は縮小し、景気は悪化していると判断されます。GDIは、経済活動を行う主体別に、「雇用者報酬」「営業余剰」「固定資本減耗」「税金(控除補助金)」の4つの項目に分類されます。「雇用者報酬」は、労働者が受け取る賃金や給与、「営業余剰」は、企業の利益、「固定資本減耗」は、生産活動に使用される機械や設備の劣化、「税金(控除補助金)」は、企業が国や地方公共団体に支払う税金などを表します。このように、GDIは国内の経済活動を包括的に把握できる重要な指標であるため、政府は経済政策の立案や効果の測定などにGDIのデータを利用しています。また、企業は将来の投資計画や事業戦略を立てる際に、GDIの動向を参考にします。私たちも、GDIについて理解を深めることで、経済の現状や将来展望をより正確に把握することができます。























