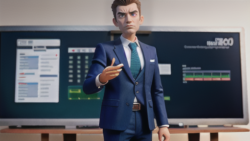債券投資
債券投資 債券投資の基礎知識:スプレッドとは?
債券への投資を検討する際に、利回りは確かに投資判断の重要な要素です。高い利回りは魅力的に映りますが、利回りだけに目を奪われて投資判断をしてしまうのは危険を伴います。なぜなら、債券は発行体や償還までの期間など、様々なリスクを抱えているからです。例えば、同じ利回りでも、倒産リスクの高い企業が発行する債券と、国が発行する債券では、リスクは大きく異なります。
このようなリスクを評価し、より安全な投資判断を行うために重要な指標の一つが「スプレッド」です。スプレッドとは、ある債券の利回りから、リスクの低い基準となる債券の利回りを差し引いたものを指します。この基準となる債券には、一般的に国債が用いられます。
スプレッドは、債券に内在するリスクの大きさを示す指標として機能します。スプレッドが大きいほど、その債券はリスクが高いと判断できます。例えば、A社の社債とB社の社債を比較した場合、A社の社債のスプレッドが大きく、B社の社債のスプレッドが小さいとします。これは、A社の社債の方がB社の社債よりもリスクが高い、つまり、A社がB社よりも倒産する可能性が高いと市場が判断していることを意味します。
このように、スプレッドは債券投資におけるリスクを測る重要な指標です。スプレッドを理解することで、利回りだけに惑われることなく、より安全で効果的な投資判断が可能になります。