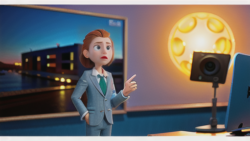株式投資
株式投資 主幹事会員の役割とは?
企業が事業拡大や新たな設備投資などのために資金を必要とする際、株式や債券を発行して、広く投資家から資金を調達することがあります。この発行活動を「引受」といい、企業に代わって投資家に証券を販売する役割を担うのが証券会社です。
大規模な資金調達を行う場合、単独の証券会社では対応が難しいケースも少なくありません。そのような場合、複数の証券会社が共同で引受を引き受けることが一般的です。この体制を「シンジケート団」と呼び、シンジケート団の中で中心的な役割を担うのが「主幹事会員」です。
主幹事会員は、発行企業と綿密に連携し、投資家にとって魅力的な発行条件や発行スケジュールを検討するなど、発行に関する全体統括を行います。また、他の証券会社をシンジケート団に勧誘する役割も担います。
さらに、主幹事会員は、投資家に対する販売活動や、証券の発行後の価格安定化のための活動など、引受業務全体を主導します。このように、主幹事会員は、企業の資金調達を成功させるために重要な役割を担っています。