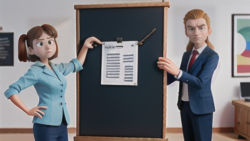投資信託
投資信託 投資信託で賢く分散投資
- 銘柄分散でリスクを減らそう投資信託で資産運用を行う際、「銘柄分散」は非常に大切です。これは、複数の異なる投資信託に投資をすることを意味します。よく、「卵を一つの籠に入れるな」という言葉を耳にすることがあるでしょう。これは投資の世界にも当てはまります。一つの会社の株や一つの投資信託だけに投資してしまうことを、「一点集中投資」と呼びますが、これは非常に危険です。例えば、ある素晴らしい会社があるとします。その会社の将来性に期待して、所有しているお金の全てをその会社の株に投資したとしましょう。しかし、その会社が予期せぬ不祥事を起こしてしまったり、業績が大きく悪化してしまう可能性もゼロではありません。もしもの時、投資していたお金が大きく減ってしまうリスクがあります。一方、銘柄分散を行えば、このようなリスクを軽減できます。複数の会社の株や債券に投資することで、仮に一つの投資先で損失が出ても、他の投資先で利益が出ていれば、損失を小さく抑えられる可能性があるからです。このように、銘柄分散は、リスクを抑えながら、安定した運用を目指すために有効な手段と言えるでしょう。