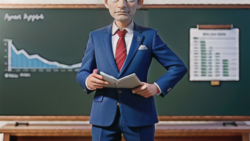その他
その他 企業年金における「単独運用」:そのメリットと注意点
- 単独運用とは企業年金基金には、従業員の将来受け取る年金を準備し、長期的に資産を増やすという重要な役割があります。そのための方法の一つとして、「単独運用」があります。単独運用とは、複数の企業年金基金の資金をまとめて運用する「合同運用」とは異なり、それぞれの企業年金基金が、預かった資金を他の年金基金とは完全に分離して、独自の方針に基づいて運用する方法です。具体的には、債券や株式といった資産に、他の年金基金と共同で購入するのではなく、直接投資を行います。債券は比較的ローリスク・ローリターン、株式はハイリスク・ハイリターンと、それぞれ異なる特徴を持つため、それぞれの企業年金基金の加入者の年齢層やリスク許容度などを考慮し、独自の判断で最適な組み合わせを選択することができます。このように、単独運用は、それぞれの企業年金基金のニーズに合わせた、柔軟で自由度の高い運用スタイルを実現できるという大きなメリットを持つ運用方法と言えます。