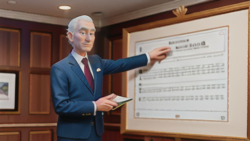経済の用語
経済の用語 工場制手工業:近代資本主義への布石
- 工場制手工業とは
工場制手工業とは、読んで字のごとく、工場で手作業によって製品を製造する生産方式です。
この方式では、資本家が多くの労働者を工場に集め、それぞれに決まった作業を分担させて、協力して一つの製品を作り上げます。このような、分業による協業体制を採用することで、従来の手工業に比べて、生産効率が飛躍的に向上しました。
工場制手工業は、英語では「マニュファクチュア」と呼ばれ、16世紀後半から18世紀後半にかけて、西ヨーロッパを中心に広まりました。そして、この工場制手工業は、後の産業革命による工場制機械工業、すなわち、私たちがよく知る近代的な工場制大生産の成立へとつながる、重要な一歩となりました。
工場制手工業は、それまでの家内工業や工房制手工業とは異なり、労働者が資本家の所有する工場で働く賃金労働者という形態が一般化していきます。これは、資本主義経済の発展を促すと同時に、労働者と資本家の関係を生み出すなど、社会構造にも大きな変化をもたらしました。