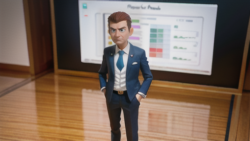投資信託
投資信託 分散投資でリスク軽減?マルチアセット投資とは
- マルチアセット投資の基礎
投資の世界には、「卵を一つの籠に盛るな」ということわざがあります。これは、資産を一つだけに集中させてしまうと、その資産の価格が下落した際に大きな損失を被るリスクがあることを示唆しています。
マルチアセット投資は、まさにこのことわざを体現した投資手法と言えるでしょう。複数の種類の資産に分散して投資を行うことで、リスクを軽減し、安定した収益の獲得を目指します。
具体的には、株式や債券だけでなく、不動産やコモディティなど、異なる特徴を持つ様々な資産に投資を行います。それぞれの資産は、景気や金利などの影響を異なる形で受けるため、ある資産の価格が下落した場合でも、別の資産の価格が上昇することで、損失を相殺したり、あるいは利益を生み出したりすることが期待できます。
このように、マルチアセット投資は、リスクを抑えながら安定的な収益を目指せる投資手法として、近年注目を集めています。