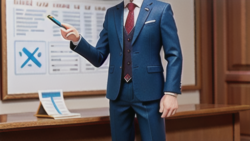債券投資
債券投資 国の借金「歳入債」:将来への影響は?
- 歳入が足りない!そんな時に国が発行する「歳入債」とは?国が国民のために様々な事業を行うには、たくさんのお金が必要です。道路や橋を作ったり、学校や病院を建てたり、年金や生活保護などの社会保障制度を維持したりと、私たちが安心して暮らせる社会を作るためには、どうしてもお金がかかってしまいます。
国は、これらの事業を行うためのお金を、主に税金によって賄っています。しかし、税金収入だけでは、必要な金額を全てまかなうことが難しい場合もあります。そんな時に、国が発行するのが「歳入債」です。
歳入債は、簡単に言うと「国の借金」のようなものです。国は歳入債を発行することで、私たち国民からお金を借り、事業を行うためのお金を確保しています。そして、その後、利息を付けて国民に返済するのです。
歳入債には、その発行目的によっていくつかの種類があります。例えば、道路や橋などの建設費用に充てるための「建設国債」、国の財政赤字を補填するための「特例国債」、年金給付の財源の一部となる「年金特例国債」などです。
特に、「特例国債」は「赤字国債」とも呼ばれ、国の財政状況を悪化させる要因の一つとして、しばしば議論の的となっています。歳入債は、国の事業を円滑に進めるために欠かせないものですが、発行しすぎると国の財政を圧迫することにもなりかねません。そのため、歳入債の発行状況や財政状況については、常に注意を払っていく必要があると言えるでしょう。